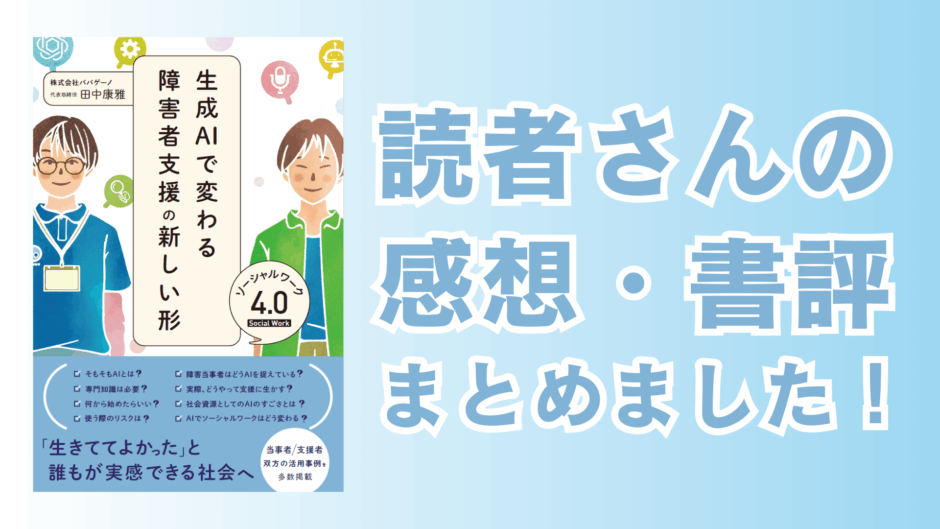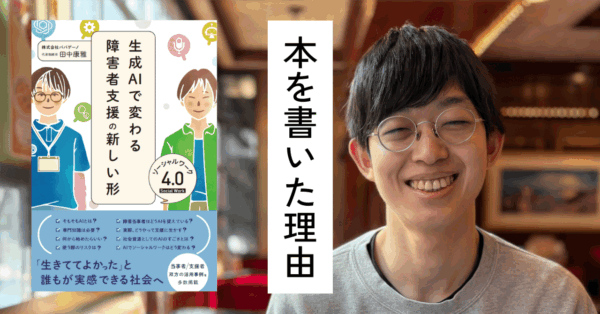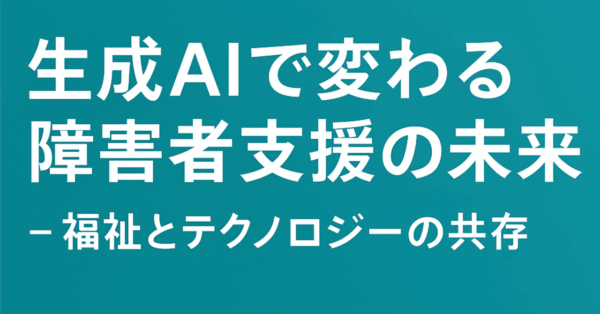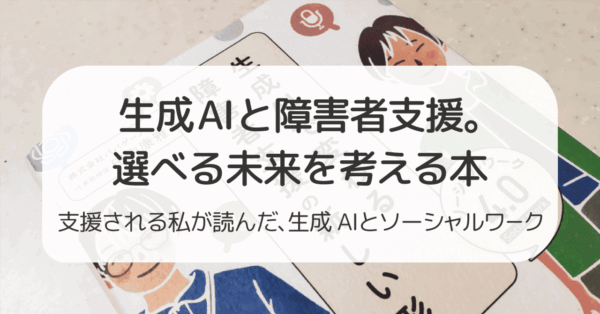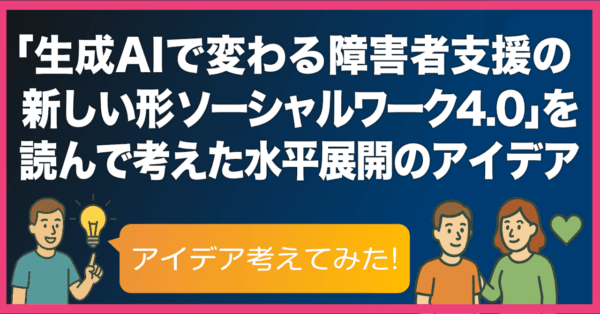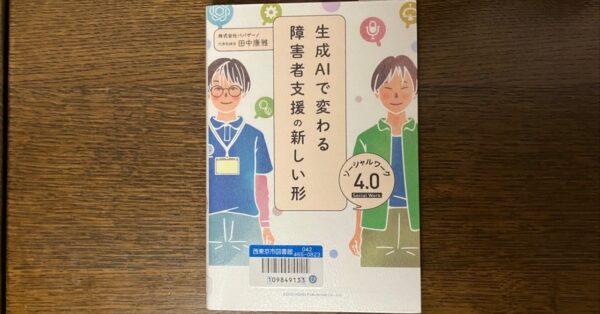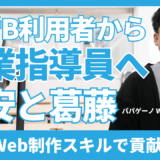書籍「生成AIで変わる障害者支援の新しい形 ソーシャルワーク4.0」を出版してから、さまざまな方から書評や感想コメントをいただいてます。この記事では、読者の方にいただいたコメントをまとめてご紹介します。
書籍「生成AIで変わる障害者支援の新しい形 ソーシャルワーク4.0」とは?
書籍「生成AIで変わる障害者支援の新しい形 ソーシャルワーク4.0」は、2025年3月11日に総合法令出版より出版された、株式会社パパゲーノ代表取締役 田中康雅による著書です。
~誰もが社会資源としてAIを使いこなす未来へ~
障害福祉とAIの融合が、個別支援のあり方を根本から変える!
本書では、最先端の生成AIを活用した障害者支援の実践事例を豊富に紹介。
ChatGPTやAIツールを活用することで、障害のある方が自分らしく働き、社会とつながる新たな可能性が開かれています。
「AIは効率化のツールではなく、社会資源である」
この視点のもと、就労継続支援B型「パパゲーノ Work & Recovery」のリアルな事例を交えながら、福祉の現場でAIがどのように活かされているのかを徹底解説。
AIで「本当の意味での個別支援」はどう実現できるのか?
「ソーシャルワーク4.0」の時代、支援者の役割はどう変わる?
障害のある方がAIを活用することで広がるキャリアの可能性とは?
ITが苦手でも大丈夫!専門知識がなくてもすぐに実践できる方法をわかりやすく解説!
AIを活用した新しい障害者支援の形を一緒に考えてみませんか?
はじめに:本当の意味での個別支援の時代
第1章:生成AIで変わる障害福祉の常識
第2章:そもそもAIとは?
第3章:対話から考える生成AIの可能性
第4章:生成AIによる支援現場のDX実践
第5章:ソーシャルワーク4.0
第6章:障害福祉業界のDX・AI活用の現状
おわりに:リカバリーの社会実装に向けて
著者:田中康雅について
株式会社パパゲーノ代表取締役CEO
ヘルスケアスタートアップでの事業開発、神奈川県立保健福祉大学大学院ヘルスイノベーション研究科でのメディアと自殺に関する研究を経て、2022 年に株式会社パパゲーノを創業。
精神・発達障害のある方が企業のDX 支援をする就労支援施設を作り、生成AI などを活用して多様な挑戦を支援。
2024年3月に「AI 支援さん」をリリース。介護、福祉、産業保健など多くの支援現場のDX に伴走。
クラウドファンディング
なお、104人の方からクラウドファンディングでご支援いただき書籍制作に挑戦していました。
書籍制作の裏側
note・ブログでの書評・感想コメント
「読書メーター」に投稿された書評・感想コメント
『生成AIで変わる障がい者支援の新しい形』を読み、AIがもたらす利用者のエンパワメントや出来なかったことを出来るようにする環境整備を可能にすることを実感した。AIは記録作成や情報提供で大きな力を発揮するが、実行や伴走は人にしかできないと感じた。利用者の目標達成に向け、命に関わらない失敗も成長の契機と捉え、苦悩や葛藤を共有しながら環境の壁を共に乗り越える姿勢こそ、AI時代のソーシャルワークの核心だと思う。障害福祉分野で働くソーシャルワーカーは必読の本だ
図書館本。生成AIを利用した障害福祉、就労継続支援B型の話。この分野では、AIは非常に有用にもかかわらず、活用例はおそらく多くない。ワクワクするような話が多かった。この方、仕事していて楽しいだろうなぁ。この本自体も、おそらくはAIの技術がふんだんに使われていると思うし、何ならこの表紙もそうじゃないかな?ただ、障碍者がAIを使ってする仕事って、それ最初からAIに任せちゃいかんの?って思ってしまった。その仕事、最終的になくならんのか?
医療業界でも、まだまだAIの利用は全然進んでいない。ちょっと本気で、chatGPTでもやりはじめないと、ついていけない気がしてきた。ただ、医療情報はまだまだ信用できないイメージがあるんだよな。
図書館にて。障害者って自分とはどこか異なる世界というか、海外のニュースを見ている感覚だった。働く環境ってどうなってるんだっけ、というところから、事業者目線の本を選んでみた。生活保護を受けながら働いて過ごすがゆえの賃金だったり、障害者支援かつ事業者支援のための生成AIだったり。ChatGPTは魔法のツールではないが、使い方の一例を知るには割と良かった。
Xに投稿された書評・感想コメント
Amazonのレビュー
実践例が書いてあります
これまでアナログ的な仕事の仕方しか知らなかったAIアレルギーの私が読んで思ったこと
いままでの仕事のやり方=車のエンジンとするなら、AIという強化バッテリーが付いた車になるということかなと思いました。少しの力で、スムーズに動くような感じですかね。省エネだったり、より効率がよくなったり楽になりそう
生成AIのリアルな活用事例を知れる
生成AIを活用した事例を知ることができ、とても参考になった。ここで語られている業界について少しでも興味や関心があれば、得られるものも多いので読んでみると良いと思う。(特にインタビューは非常に興味深く、自分の知らない事を知る良い機会だったので、是非一読をオススメしたい)
時間を有効に使う
新しい支援のあり方、新しい技術として、多くの方に読んで頂き、導入を勧めたい
新しい支援の形を模索する旅に一人でも多くの人が参加するきっかけに
高齢者・障害児者支援にかれこれ15年ほど携わってきたものからの感想です。
3つの点があります。
①支援者としての可能性
目の前のご利用者様にかかわる中でずっと感じるのは、一人一人とのかかわりの中で多くのことを学ばせていただいているという実感です。多くのご利用者様とかかわることで、たくさんの学びをいただいてきました。AIの力が支援者にとってとってもありがたいきっかけになるのは、15年という歳月を費やさなくても、多くの事例を踏まえた支援方法にたどり着けたり、多くの提案をもらえるという社会資源としてのAI使用の可能性です。あなたも今日から深い見地に基づいた最適解を探しやすい旅に出ることが容易に可能になります。
②障害当事者とAIの可能性
社会資源としてのAIの可能性は、驚くべきことに支援者の支援技術向上だけでなく、障害者の方々に、第三の支援者としてかかわってくれます。AIがどれだけ台頭しても、直接的な支援をする「人」の代わりにはなりえないといわれてきました。一方、AIだからこそできる支援が多く存在することを、本書では実践例と当事者インタビューで知らせてくれます。これからもより多くの実践事例が生まれることを予感させてくれますし、AIを隣においてどのようにかかわっていくことができるのかワクワクさせてくれます。
③それでも変わらないソーシャルワーク4.0とは?
AIにかできない支援があることと一方で、次のソーシャルワークは、一緒に行動することだと筆者は位置づけてします。知識や経験を得ることよりも実践行動により多くの時間をさけるのではないか?それは、支援に携わる誰もが望んでいる未来な気がしています。
私自身が感じたのと同じく一人でも多くの人が、新しい支援の形を模索する行動のきっかけになるのではと期待させてくれる本です。
新しい支援のカタチ
障害支援に筆者がいかに精力的に、優しい心をこめて取り組んているのか、伝わります。
本当の「支援」に向かう際の必読書です。
福祉およびAIについて知るための入門書としても最適!
精神保健福祉士になるための勉強をしている社会人です。本のタイトルにひかれて予約し購入、読み終えました。「どの仕事をしているひとにも届いてほしいな」と思ったのでレビューを書きます。
読んでみて感じたのは「福祉についても生成AIについても最初の一冊として読みやすい」ことでした。DXやICT分野はもちろん、精神疾患・障害の分野について語られる場面、語る人はかつてより増えたように思います。しかし、その一方で、どちらの分野も「わかりやすい」部分だけの認識に留まっているようにも感じています。DXなら「なんとなく便利」、精神疾患・障害なら「なんとなく大変そう」。人によっては「どちらも複雑で難しそう」と感じているケースもあるかもしれません。そんな敷居をこの一冊は突き崩して解説してくれています。
ふと考えてみれば、確かに福祉支援もAI開発も専門知識が必要な分野のイメージが自分にはありますし、そこは本書を読んでも変わらないのです。しかし、目次を見てもわかるように、そもそも「障害福祉とは何か」「AIってなんだ?何ができるのか?」「当事者はどう考えているのか?」「障害者支援のDXどんな事例があるのか」が順を追って紹介してくれています。加えて、社会的な背景もデータとともに解説してくれています。つまり、興味を持ったところを読んでみてもいいし、順を追ってまるで「パパゲーノ」の見学をしている感覚で読んでもいいし。DXやAI、そして障害福祉に無縁で居られるひとはほぼいないだろうと思うと、とても読む意義の深いそして使いやすい一冊だと思いました。写真のようにページ数もちょうど良いです。
著者の田中さんが社名に込めた「生きててよかったと誰もが実感できる社会へ」に強く共感した自分にとっては、きっとどの仕事を志していても、どの仕事をしていても「エールになる言葉もちりばめられている」ように感じました。バーンアウトしそうになるタイミングにも読みます。
AIと共に歩む未来
子どもたちの未来の選択肢として就労継続支援施設を見学し、その施設でのAIを取り入れた支援に興味を抱いてこの本を購入しました。予約特典として著者の田中さんと直接お話しできたことも、とても貴重な体験でした。
AIは私にとってまだ馴染みのない分野ですが、その可能性を知ることで社会にどのような影響を与えられるのかを考えると、非常にワクワクしました。障害を持つ方々がより良い社会で生きるために、AI技術が広く活用され、当たり前のように語られる未来を願っています。
私自身も最近になって自分の障害を自覚し、こちらの施設で実際に働ける可能性が開けた事に胸が躍りました。この本が多くの人にとってより良い選択肢をもたらしてくれる事に期待しています。
これからの就労継続支援のあり方を考えるために必要な本
この本を読んで、こういったサービスの現実的な姿を知ることができました。リカバリーを実装するという理念にとても共感を受けました。これからの就労継続支援のあり方としてとても学ぶことができる本だと思います。
福祉の未来を考えるすべての人に読んでほしい一冊
AIと福祉という一見遠いように思えるテーマですが、本書はとても丁寧に、かつ実践的にその可能性を教えてくれました。
特に印象的だったのは、「福祉における支援の在り方が“リハビリテーション”から“リカバリー”へと変わっていく」という視点。これはまさに、支援のあり方そのものが、利用者本人の主体性や可能性に焦点を当てていくという未来の方向性であり、ワクワクしました。
さらに、実際の障害のある当事者の方が生成AIを使ってみたリアルな声も紹介されており、「こんなふうに活用できるのか」と具体的なイメージを持つことができました。
専門用語も噛み砕いて説明されており、AIを使ったことがない人でもスッと読める内容なので、業界初心者にもおすすめです。
「生成AIが広がる今、支援者に求められる視点とは?」
福祉業界でこれからとても大事になる問いの一つに、きっとヒントをくれる一冊です。
なかなかDX化が進まない福祉業界
お金も時間も心の余裕もないままに離職率も高く、不満も多い業界だと感じています。
この本を手に取る福祉職の人が増えて、AIやITにまずは興味を持つ人が増えてくれたら嬉しいなと感じています。
リカバリーとテクノロジーの融合
田中康雅さんの『生成AIで変わる障害者支援の新しい形 ソーシャルワーク4.0』を読んで、生成AIが障害者支援に革新をもたらす可能性を強く感じました。
特に、AIを活用した個別支援の最適化や支援者の業務負担軽減の具体例が印象的で、新しいリカバリーロードマップの研究と実現に向けた意欲が高まりました。
また、本書が対話の重要性を強調し、障害当事者の声を多数掲載している点も心に残りました。当事者と支援者がAIの使い方について対話を重ねることで、支援の質が向上し、これが新しい障害者支援の形を生み出す大きなスタートになると感じています。
AIを社会資源として位置付け、対話を通じて障害者支援の新たな形を模索する取り組みを、ぜひ実践していきたいと考えています。
昔からテクノロジーは障害のある方にとって大きな助けであり力となってきました。車椅子、補聴器、インターネット、音声読み上げソフト、メガネなど困難を克服するためのテクノロジーは今までたくさん発明されてきました。これからの時代はAI。未来が楽しみです。
支援者必見。特に障害者就労関連で働いている方に特にお勧めします。
東京都で就労継続支援B型事業所パパゲーノを経営されている方の書籍です。
障害者支援、特に就労支援と関連が深い内容ですが、それ以外の分野で働いている方、また高齢分野で働いている方、障害当事者の方にもお勧めできる内容となっています。
パパゲーノさんでの取り組み事例が具体的に載っていたり、当事者の方が生成AIをどのように使っているかのインタビュー部分もある等、書籍の全てではなくても参考になる部分はあるのではないでしょうか。
実際のAIの使い方等は調べたりする必要もあると思いますが、実践例でどのように作成すれば良いのかも載っているのも良いと思いました。
今後、AIに仕事を奪われるという意見もありますが、そうではなくてAIを活用することでより良い支援ができていく、さらには当事者の方の可能性も大きく広がるということを、この書籍を読み改めて感じました。
文章も読みやすく、表や画像なども多くてすんなり読めますよ。
ITが苦手でも読んでほしい本
福祉業界の方にはぜひ読んでほしいと思います。
生成AIというと難しそうという感じがするかもしれませんが、この本では簡易な表現で書いているので読みやすくお勧めです。
私はSEなのですが、福祉業界にはまだまだ紙が多いということを知って驚きました。利用者さんの「できる喜び」を増やすためにもぜひITを取り入れてほしいと思います。
これからの時代、AIによって加速的に世界は変化していくと思います。そんな世界に従業員の方も、利用者の方も取り残されないためにもぜひ読んでほしいです。
まずはChatGPTなどに登録して、困ったことをちょっと相談してみてほしいです。そこからAIの使い方というのは広まっていきます。
全福祉人が一度は読んでおいた方がいい
AIがこれだけ世の中で注目されているにも関わらず、福祉業界はまだまだAIとの接点を見出しきれていません。それどころか福祉の中でAIをどのように活用するのか、という議論すらまだほとんどありません。
田中やすまささんのこの書籍は、AIを「技術」とか「テクノロジー」ではなく「社会資源」として取り上げ、まさに社会資源を活用して人を支援するソーシャルワーカーへの気づきのきっかけにしていること、そして支援者だけでなく支援業務の中にあるさまざまな煩雑な業務をいかに人と役割分担しながら圧縮化していけるかという具体的な事例についても提案があり、さらに障がい当事者の選択肢が、AIによって広がることについても当事者のインタビューから示している。
2時間もあれば読み切ることができるこの書籍には、ノウハウというよりも「AIを活用してみようかな?」と思わず感じさせられるような事例、提案、きっかけが随所に散りばめられている。
特にDXが非常に遅れている福祉業界だからこそ、支援者や福祉経営に携わっている方は一度手に取って読んでみて損はないと思う。
新しい形の障がい者支援
非常に興味深い内容で大変勉強になった本です。
恥ずかしながら障がい者支援への理解が足りていなく、
この本を読むまで障害福祉という単語も知りませんでした。
これからの新しい障がい者支援にパパゲーノさんが尽力してくれることが楽しみです。
新時代
障害福祉分野の将来が明るくなる時代が
やっと来ている。大いに期待、想像できるものとなりました
初心忘れず突き進んで下さい。
福祉 AI スタートアップの交差点となる1冊
福祉・AI・スタートアップと一見親和性の乏しい要素が見事に融合し、また、実行されており興味のある方はもちろん、社会課題の解決に関心のあるすべての人にとって、本書は示唆に富んだ一冊です。特に、インパクトがあったのは創業からの軌跡です。著者である田中氏は神奈川県立保健福祉大学大学院ヘルスイノベーション研究科に在学中に起業されています。
大学院での学びを実践的な知識として昇華させ、障害者支援に革新をもたらす方法が提案された一冊です。学問的な視点と現場での応用が見事に融合し、AIと福祉がどのように交差するのかを具体的に示しており、新たな障害者支援のあり方を考えさせられる内容となっています。
いろんな人に読んでほしい
さまざま人の可能性を広げるツールとして生成AIはもっと身近になっていくのかなと思いました。
そのための理解の一歩目として非常に良い本だなと思いました。
障害者支援に新しい風をもたらすかも
実際に活用されている利用者さんとの対談が印象的だった。AIの強み、まだ弱い部分を理解した上で上手く付き合っている。障害者支援について一気に変化することは難しいだろうけど、新しい風を感じた1冊。購入してよかった!ソーシャルワークについても触れており、大変勉強になった。
おすすめです!
AIを活用したソーシャルワークの事例に加えて、事業所運営にも役立つ情報が満載です!
本書が“対話のきっかけ”になることを願っています
「生成AIで変わる障害者支援の新しい形 ソーシャルワーク4.0」は、多くの方々から多様な感想や気づきをいただき、単なる一冊の書籍を読む体験にとどまらず“対話のきっかけ”として広がり続けています。
レビューやコメントを拝見すると、AIを「効率化の道具」としてだけでなく、「社会資源」としてとらえる視点に共感いただけたこと、また支援者や当事者、そして福祉に関心を寄せる読者の皆さまがそれぞれの立場から新しい可能性を見出してくださったことに、喜びを感じています。約10万文字の原稿執筆は大変でしたが、書いてよかったです。
AIと福祉の融合はまだ始まったばかりです。この本が、現場での実践や新しい支援の形を模索する第一歩となり、一人でも多くの方が「AIと共に歩む未来」を考えるきっかけとなれば幸いです。
引き続き、皆さまからの感想や実践の声を楽しみにしています。